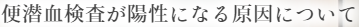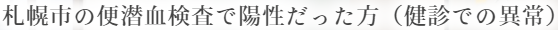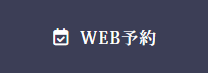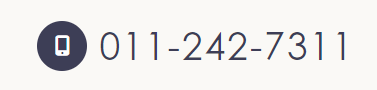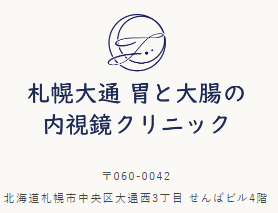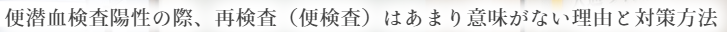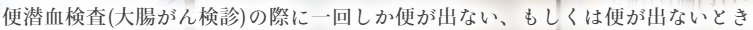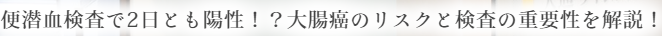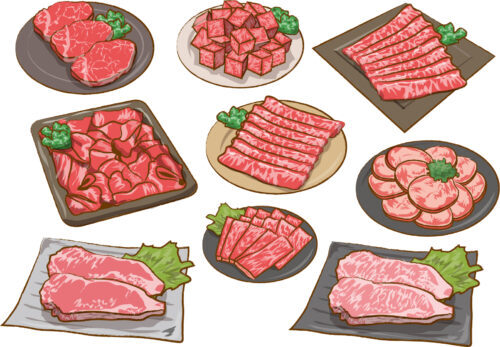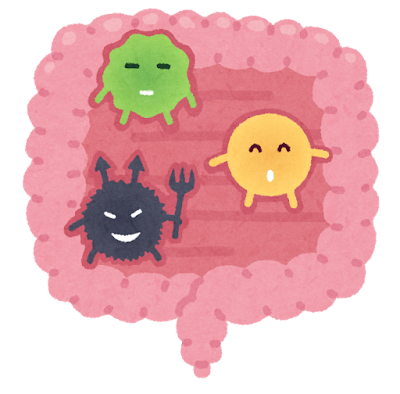2025年1月16日

『健診で貧血といわれたけど原因はなんですか?』

『出血はないですが貧血になるんですか?』

『特に症状はなくても貧血にはなるんですか?』

そんな疑問に答えていきます。

目次
1. 貧血とは?一般的な症状と原因

貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常値よりも少ない状態を指します。
原因としては、鉄分の不足や大量の出血、自己免疫疾患、遺伝的な要因などがあります。

1.1. 貧血の主な症状
貧血の主な症状には、いくつかの特徴があります。

まず、日常的に感じる疲れやすさです。これは、酸素を運ぶ赤血球が不足するために起こるものです。また、息切れしやすくなることもあります。これは、運動時や階段を登る時などに特に顕著です。

その他、頭痛やめまい、不眠や集中力の低下にも気をつける必要があります。さらに、顔色が悪くなったり、手足の冷えを感じたりすることもあります。

1.2. 鉄欠乏性貧血の原因
鉄欠乏性貧血の主な原因は、体内の鉄分の不足です。特に女性は、月経による出血で鉄分を失うため、鉄欠乏性貧血になりやすいです。

次に、食事からの鉄分摂取が不十分な場合もあります。肉類や緑黄色野菜を避ける食生活が続くと、鉄分が不足しやすくなります。

成長期の子供や若者も鉄欠乏性貧血になりやすいです。この時期には体の成長に伴って多くの鉄分が必要となるためです。さらに、大量の出血が続いた場合や、消化管の障害による鉄分の吸収不良も原因となります。
1.3. 他の貧血の種類とその特徴
貧血には、鉄欠乏性貧血以外にもいくつかの種類があります。その一つが溶血性貧血です。これは赤血球が通常よりも早く壊れるために起こるもので、遺伝的な要因や自己免疫疾患が原因となることが多いです。

次に、巨赤芽球性貧血があります。これはビタミンB12や葉酸の不足によるもので、赤血球の大きさが異常になり、正常に機能しないためです。

また、再生不良性貧血という貧血もあります。これは骨髄の機能が低下し、赤血球が十分に生産されなくなるために起こります。

さらに、慢性疾患に関連した貧血もあります。これは、慢性的な病気が原因で赤血球の生成が妨げられる状態です。例えば、慢性腎臓病が進行すると、エリスロポエチンというホルモンの不足により貧血が発生します。

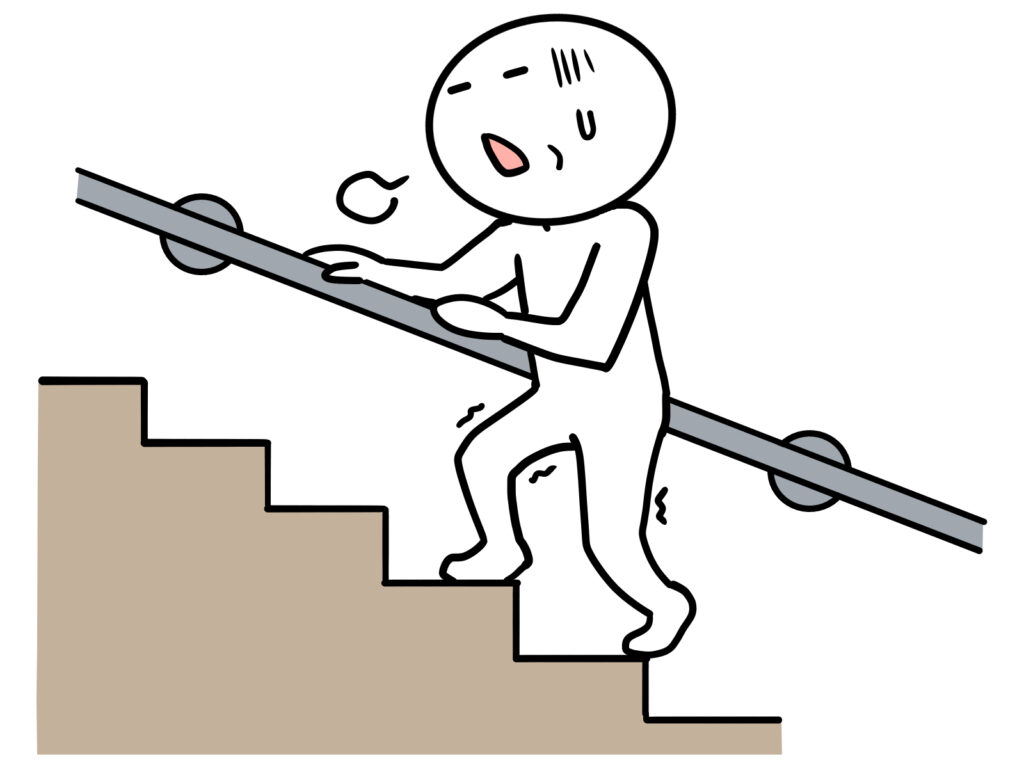

2. 札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックの紹介

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックは、貧血精査の為の内視鏡検査を行っております。

2.1. 内視鏡による消化管出血の検索
札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、内視鏡を用いた消化管出血の検査が行われています。

内視鏡検査は、消化管内の詳細な映像を提供するため、出血の原因となる病変を迅速に特定することが可能です。初期診断から治療計画の立案まで、患者様一人ひとりに合わせた対応を行っています。

さらに、専門のスタッフがサポートするため、初めての方でも安心して検査を受けられる環境が整っています。
2.2. 鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査
当院では、鎮静剤を使用して無痛内視鏡検査を実施しています。

これにより、内視鏡検査に対する不安や恐怖を軽減することができます。また、検査中の痛みを最小限に抑えるため、リラックスして検査を受けることができます。

専門の医師が適切な鎮静剤の量を調整し、患者様の状態に合わせて安全に検査を行っています。検査後もすぐに日常生活に戻れることが多いため、忙しい方にもおすすめです。
2.3. WEB予約で24時間いつでも予約可能
札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、24時間いつでもWEB予約が可能です。

これにより、忙しい方でも都合の良い時間に予約できます。インターネットを通じて簡単に予約手続きができるため、予約のための電話や直接来院する必要がありません。

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックで内視鏡をご希望の方は以下のリンクからご予約ください。


3. 消化管出血と貧血の関係

消化管出血とは、消化管内部で出血が発生する状態を指します。それにより、鉄分が失われるため貧血が引き起こされる可能性があります。

3.1. 消化管出血による貧血のメカニズム
消化管出血は、胃や腸などの消化管からの出血を言います。潰瘍や癌などで出血を起こすケースが多いです。
大出血が起こると、一度に大量の血液が失われるため、急性貧血を引き起こします。小さな出血が持続する場合は、慢性貧血の原因となります。

血液の成分のうち、大部分は鉄分なので、消化管出血によって鉄分が失われると、鉄欠乏性貧血が発生します。
3.2. 消化管出血の症状と早期発見の重要性
消化管出血の症状は、多岐にわたります。お腹の痛みや出血の量によるショックなどが発生します。便に血が混じることもありますが、血液量が多くないと気が付かない事もあります。

貧血の症状としては、息切れや倦怠感が挙げられます。さらに、顔色が青白くなることや、手足の冷えも症状の一部です。これらを感じたら、自己診断せず専門医の診察を受けることが重要です。
3.3. 自己チェックできるサイン
消化管出血を自己チェックする方法として、いくつかのサインがあります。まずは便の色を確認することです。黒っぽい便が続く場合は、胃潰瘍などの上部消化管出血の可能性があります。

次に、貧血の症状が出ていないか確認しましょう。息切れや疲労感、顔色の悪さが続くときは注意が必要です。これらの症状は見逃しがちですが、早期の治療が大切です。

さらに、体重減少や食欲不振も消化管出血のサインです。これらの症状が続く場合は、自己チェックを怠らず医療機関を受診することが必要です。早期発見と適切な治療が健康維持の鍵です。



4. 内視鏡検査の役割

内視鏡検査は、消化管の内部を直接見ることができるため、精度が高く、詳細な診断が可能となります。

4.1. 内視鏡検査とは?
内視鏡検査は、細長い管にカメラを取り付けた内視鏡を使って体内を調べる検査です。このカメラで撮影した映像をモニターで確認しながら、医師が狙った部位を詳しく観察します。

内視鏡の役割としては、病気の早期発見が挙げられます。例えば、胃や大腸のがんは、初期段階で発見できれば治療成績が良いことが知られています。また、慢性の炎症やポリープなども早期に発見できるため、症状が現れる前に対策をとることができるのです。
4.2. 胃内視鏡検査でわかること
胃内視鏡検査(上部内視鏡)は、胃の内部を詳細に調査する方法です。例えば、胃潰瘍や慢性胃炎、そして胃がんの早期発見が主な目的です。この検査では、内視鏡を口から挿入して胃の内部を直接観察します。また、小さなポリープや炎症といった異常も見逃さずに確認することができるので、非常に有用です。

さらに、異常が発見された場合には、その場で組織を取り出して病理検査を行うことができます。また、慢性胃炎や胃潰瘍の進行具合を定期的にチェックすることで、症状の悪化を防ぐことも可能です。
4.3. 大腸内視鏡検査の重要性
大腸内視鏡検査は、大腸の内部を調べるための重要な検査です。この検査は、主に大腸がんの早期発見やポリープの発見・除去が目的となります。

大腸がんは、早期発見で治療の成功率が非常に高くなることが知られています。ですから、定期的な大腸内視鏡検査が推奨されております。ポリープはがん化することがあるため、早期に発見し除去することが重要です。

大腸内視鏡検査は、症状がなくても定期的に受けることが大切です。特に40歳以上の人や家族に大腸がんの患者がいる人は、早めの検査を心がけると良いでしょう。健康維持には欠かせない検査です。



5. 貧血の診断と治療

貧血は血液中の赤血球やヘモグロビンの量が正常範囲よりも低くなる状態のことです。
この状態は、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

5.1. 貧血の診断方法
貧血の診断には、まず血液検査が行われます。

これにより、ヘモグロビンの濃度や赤血球の数が測定されます。また、赤血球の大きさや形も確認されます。

次に、鉄分やビタミンB12、葉酸の欠乏を調べるための血液検査も実施されます。これらの検査結果をもとに、医師は貧血の原因を特定します。

そして、必要に応じてさらなる検査や画像診断が行われることがあります。これにより、正確な診断が可能となるのです。
5.2. 治療に使用される薬品とその効果
貧血の治療には、原因に応じた薬品が使用されます。

鉄分欠乏による貧血の場合、鉄剤が処方されます。これにより、体内の鉄分量が改善され、赤血球の生成が促進されます。

また、ビタミンB12や葉酸の欠乏が原因の場合、これらを補う薬剤が用いられます。これらの栄養素は、赤血球の形成や成熟に不可欠です。

さらに、慢性疾患に伴う貧血であれば、その基礎疾患の治療も併せて行われます。
5.3. 日常生活での注意点と改善方法
貧血を改善するためには、日常生活での注意が欠かせません。

まず、バランスの取れた食事が重要です。鉄分を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。例えば、レバーやほうれん草、赤身の肉などが挙げられます。

さらに、規則正しい生活リズムを保つことも大切です。十分な睡眠と適度な運動を心がけることで、体調が整いやすくなります。このように、継続的な努力が貧血の改善につながるのです。



6. 貧血予防のためのライフスタイル

日常生活で貧血を予防するためには、特定のライフスタイルを心掛けることが重要です。

6.1. 栄養バランスの取れた食事
貧血予防には、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。

特に、鉄分を多く含む食材を意識的に摂取することが大事です。レバーやほうれん草、大豆製品などが鉄分豊富な食材です。ビタミンCも共に摂ると、鉄分の吸収が良くなるので、オレンジやピーマンなどを一緒に食べると良いです。

また、タンパク質やビタミンB12も大切ですので、肉や魚、卵をバランス良く取り入れましょう。その結果、体の中で効率よく鉄分を活用でき、貧血予防につながります。
6.2. 適度な運動の重要性
適度な運動は、貧血予防においても重要な役割を果たします。

まず、運動によって血流が良くなるため、栄養素の供給が促進されます。ウォーキングやヨガなどの軽い運動を毎日の生活に取り入れることで、体全体の健康を向上させることができます。

さらに、運動にはストレス解消の効果もありますので、心の健康も維持できます。運動を継続することで、長期的に貧血を予防することが期待できます。
6.3. 定期的な健康チェックのすすめ
貧血予防のためには、定期的な健康チェックも欠かせません。

目に見えない体の異変を早期に見つけるためには、定期的に血液検査を受けることが重要です。特に、女性は月経の影響で貧血になりやすいので、定期的なチェックが必要です。

また、生活習慣の改善や栄養補給の効果を確認する上でも、定期的な検査が役立ちます。早期発見と適切な対応により、健康を維持することができるでしょう。

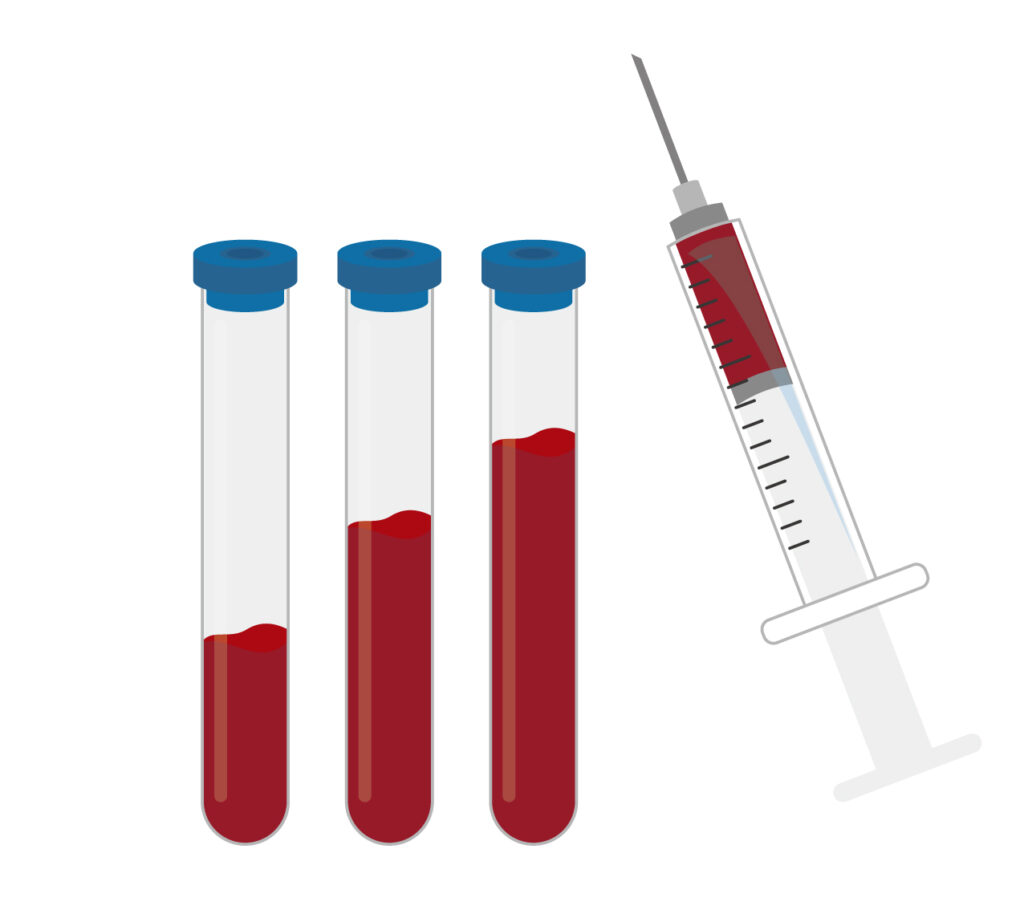

7. 消化管出血の予防策

消化管出血は、胃や腸の内部で発生する深刻な症状です。
予防には、日常生活からの取り組みが重要になります。

7.1. 食生活の注意点
まず、食事を規則正しく摂ることが大切です。

過度な飲食や脂っこい食事は避け、消化に良い食べ物を選びましょう。野菜や果物を豊富に摂取し、食物繊維をしっかりとることが望ましいです。

また、アルコールやカフェインの摂取を控えることも必要です。特に空腹のまま飲酒すると、胃酸が増えて消化管を痛めやすいです。

次に、刺激物を控えます。辛い食べ物や酸味の強い食品は胃腸に負担を掛けるため、適度にすることが求められます。少量ずつゆっくり食べることで、胃腸への負担を減らせます。
7.2. 定期検診の重要性
消化管の健康を守るためには、定期検診が不可欠です

定期的に医師に診てもらうことで、早期の異常発見が可能になります。内視鏡検査や超音波検査を行うことで、内部の状態を正確に確認できます。

また、ピロリ菌の検査や血液検査も重要です。これにより、目に見えない異常を発見することができます。

さらに、自覚症状がなくても定期的に検診を受けることが、重篤な病気の予防にもつながります。検査結果を基に適切な治療を受けることで、健康維持が図れます。
7.3. ストレス管理と生活習慣
ストレスは消化管にも大きな影響を与えます。適度な休息とリラックスを心掛けることが必要です。ストレスをため込まず、運動や趣味を通じて発散することが良いでしょう。

さらに、ロキソニンやイブプロフェンなどの痛み止めで胃潰瘍になるリスクがありますので内服薬にも注意しましょう。

こうした習慣を心掛けることで、消化管の健康を長く保つことができます。




大腸内視鏡検査は札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックがおすすめです!



・関連記事