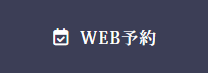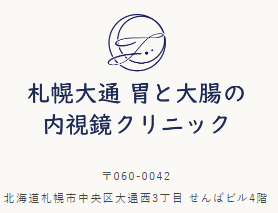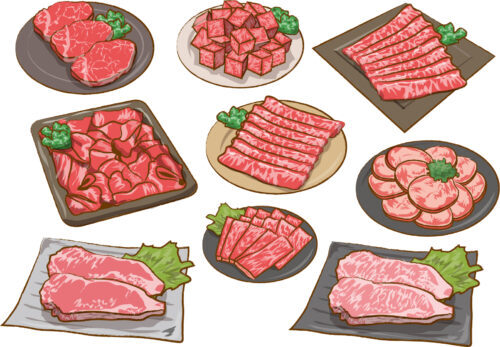2025年3月19日

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック院長の福田です。

本日は、多くの方が気にされている食生活と大腸の健康について、特に近年利用が増えている人工甘味料の影響に焦点を当ててお話ししたいと思います。

「カロリーゼロ」「シュガーレス」といった言葉が溢れる食品や飲料。ダイエットや血糖値管理のために、砂糖の代わりに人工甘味料を積極的に摂取している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、
『甘味料って身体にとってよくないのでは?』
『大腸などの消化管にも何らかの影響があるのではないか?』

そんな疑問が湧いてくる方も多いと思います。
今回のコラムでは、このような疑問にお答えするために、人工甘味料の中でも発癌性の可能性があるアスパルテームを含め、最新の研究や情報を基に、大腸との関連性について詳しく解説していきます。

目次
なぜ今、人工甘味料と大腸の健康が気になるのか?

近年、食生活の欧米化や加工食品の摂取増加に伴い、大腸がんをはじめとする大腸の疾患が増加傾向にあります。

大腸は、私たちの健康を維持する上で非常に重要な役割を担っており、その環境を良好に保つことが全身の健康にも繋がります。
人工甘味料は、砂糖に比べて少量で強い甘味を感じられるため、様々な食品に利用されています。しかし、その一方で、長期的な摂取による影響については、まだ十分に解明されていない部分も存在します。特に、腸内細菌叢や肥満への影響が注目されております。



加糖飲料・人工甘味料入り飲料とがん死亡リスクの関連

米国の大規模疫学研究により、加糖飲料や人工甘味料入り飲料の摂取が、一部のがんによる死亡リスクを肥満とは無関係に上昇させる可能性が示されました。

研究では、約93万人を約28年間追跡調査し、加糖飲料・人工甘味料入り飲料の摂取とがん死亡との関係を分析しました(https://aacrjournals.org/cebp/article-abstract/31/10/1907/709398/Sugar-and-Artificially-Sweetened-Beverages-and)。
結果、加糖飲料を1日2杯以上飲む人は、大腸がん、非ホジキンリンパ腫、腎臓がんによる死亡リスクがそれぞれ1.07倍、1.14倍、1.14倍に上昇していました。また、人工甘味料入り飲料を多く摂取する人では、膵臓がんの死亡リスクが1.11倍に増加していました。
この研究から、加糖飲料や人工甘味料入り飲料の過剰摂取ががんのリスク因子となる可能性があり、適量を心がけることが重要であると考えられます。

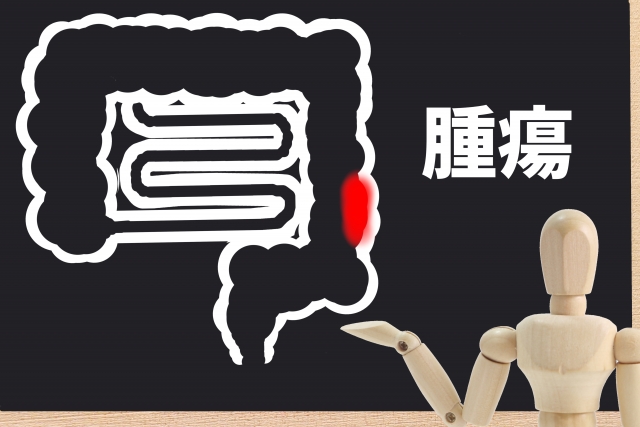

人工甘味料の種類と特徴

まず、一般的に使用されている主な人工甘味料の種類とその特徴について見ていきましょう

- アスパルテーム: 甘味が強く、清涼飲料水、ガム、お菓子などに広く使用されています。摂取すると体内でアミノ酸とメタノールに分解されます。メタノールの安全性については議論がありますが、現在の日本人の平均摂取量では問題ないとされています。
- スクラロース: 砂糖に近い甘味を持ち、熱にも安定しているため、幅広い食品に利用されています。研究によっては、ブドウ糖不耐症を引き起こす可能性が示唆されています。
- サッカリン: 古くから使用されている人工甘味料で、砂糖の数百倍の甘味があります。こちらも、ブドウ糖不耐症との関連が研究で示唆されています。
- ステビア: 天然由来の甘味料で、砂糖の数十倍の甘味があります。試験されたレベルでは、耐糖能に影響を与えなかったと報告されています。
- ネオテーム、アセスルファムK: 他にも様々な人工甘味料が存在し、それぞれ甘味度や安定性などの特徴が異なります。

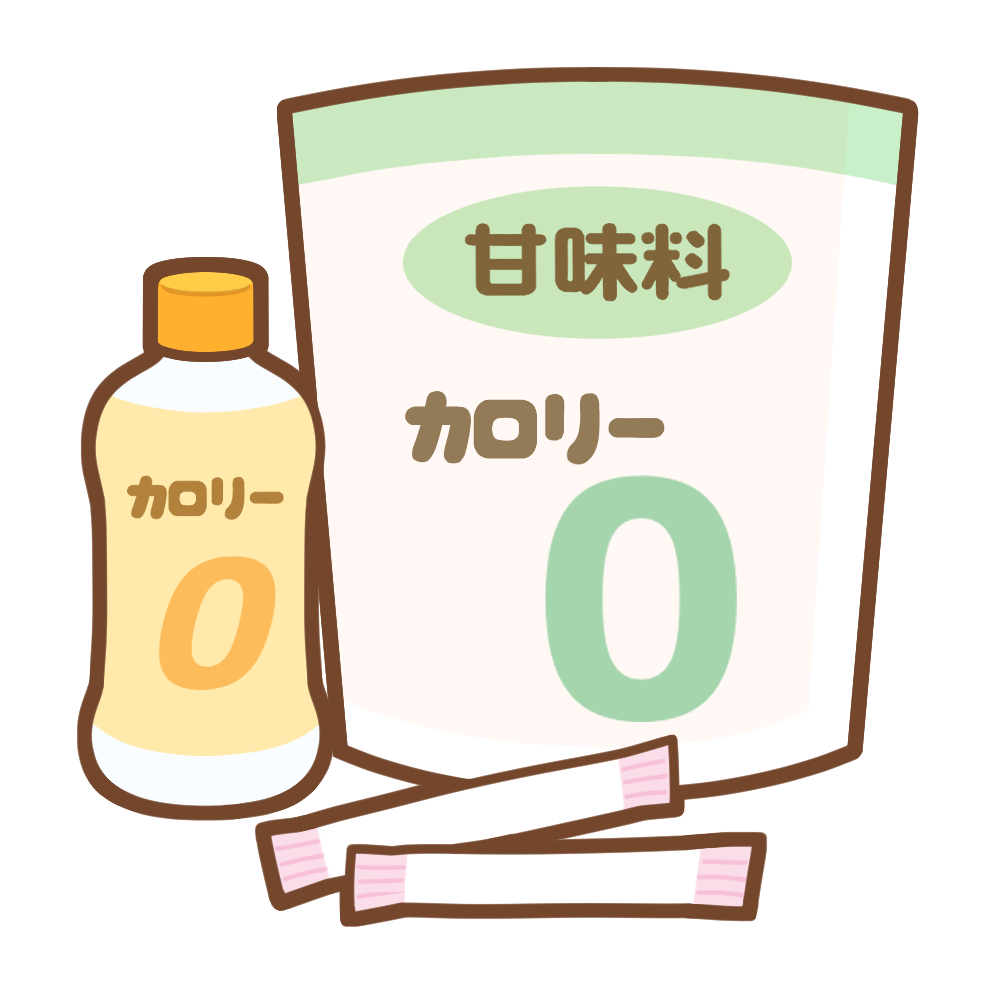

最新研究から見えてきた人工甘味料と腸内細菌の関係

近年、人工甘味料が私たちの腸内細菌叢にどのような影響を与えるのかについて、多くの研究が行われています。

ある研究では、スクラロースとサッカリンの摂取が、体をブドウ糖不耐症へと近づける可能性が示唆されています。この状態が続くと、体重増加や糖尿病のリスクが高まることが懸念されます。一方で、アスパルテームとステビアは、試験で摂取したレベルでは耐糖能に影響を与えなかったと報告されています。
またある研究によると、人工甘味料によって腸内細菌叢の乱れ、血糖値に悪影響を及ぼす可能性も報告されています。すべての人に同じ影響があるわけではないにせよ、一部の人においては、人工甘味料によって糖の代謝が混乱させられる可能性があります。

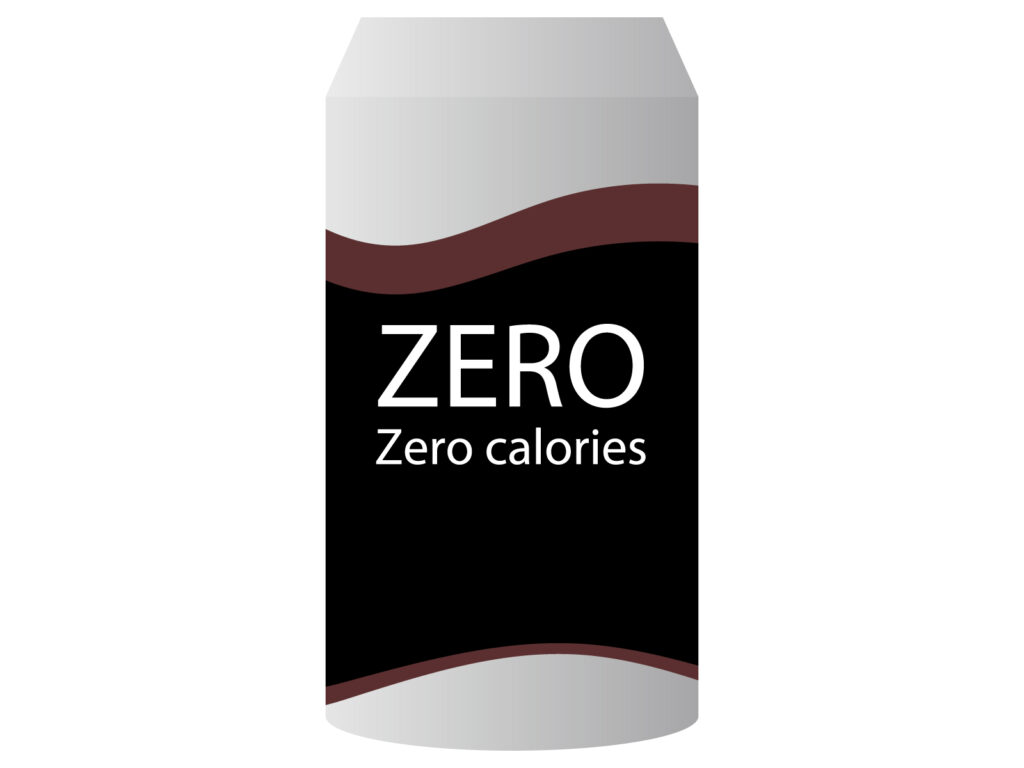

アスパルテームの安全性について

アスパルテームは、その安全性について長年にわたり議論がなされてきました。

体内で分解される際に生成されるメタノールは猛毒であるという指摘もあります。しかし、一般的には、アスパルテームの摂取によって生成されるメタノールの量はごく微量であり、通常の食品から摂取する量と比較しても問題ないとされています。
ただし、フェニルケトン尿症という遺伝性疾患を持つ方は、アスパルテームに含まれるフェニルアラニンを適切に代謝できないため、摂取を避ける必要があります。
現時点での科学的な知見に基づけば、アスパルテームは、適切な摂取量であれば一般的に問題はないと考えられています。しかし、今回の研究で示唆されたように、腸内細菌叢への影響は個人差がある可能性があり、それが長期的な健康にどのような影響を与えるのか、引き続き注意深く見守る必要があるでしょう。



大腸の健康を維持するために大切なこと

人工甘味料の影響も気になるところですが、大腸の健康を維持するためには、日々の生活習慣全体を見直すことが非常に重要です。

バランスの取れた食生活
- 食物繊維を積極的に摂取する: 食物繊維は、腸内環境を整え、便通を促進するだけでなく、発がん性物質などの有害物質を体外へ排出する働きがあります。水溶性食物繊維(こんにゃく、果物、海藻類、きのこ類など)と不溶性食物繊維(穀類、豆類、野菜類など)をバランス良く摂ることが大切です。1日の摂取推奨量は成人で約20~25グラムですが、日本人の平均摂取量は下回る傾向にあるため、意識して摂取するようにしましょう。
- 発酵食品やプロバイオティクスを活用する: ヨーグルト、納豆、キムチなどの発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす効果が期待できます。プロバイオティクスは、腸の働きをサポートし、便通を促進する可能性があります。
- 脂肪分の多い食事や加工肉の摂取を控える: これらの食品の過剰摂取は、大腸がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
・関連記事
適度な運動
- 運動不足は、腸の蠕動運動を低下させ、便秘の原因となることがあります。適度な運動習慣を身につけ、大腸の働きを活発に保ちましょう。
規則正しい生活
- 不規則な生活は、自律神経の乱れを引き起こし、便秘などの消化器系の不調に繋がることがあります。規則正しい睡眠や排便の習慣を心がけましょう。
定期的な大腸がん検診
- 大腸がんは、初期には自覚症状がほとんどないため、早期発見のためには定期的な検診が非常に重要です。
- 便潜血検査: 40歳以上の方には、年1回の便潜血検査が推奨されています。これは、便に目に見えない血液が混じっていないかを調べる検査で、大腸がんによる死亡率を減らす効果が科学的に証明されています。ただし、便潜血検査が陰性でも大腸がんが隠れている可能性や、痔など他の原因で陽性となる場合もあるため、注意が必要です。
- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ): 便潜血検査で陽性となった場合や、血便、便通異常などの症状がある場合には、大腸内視鏡検査が必要です。大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の粘膜を直接観察できるため、小さなポリープや早期のがんを発見するのに非常に有効な検査です。ポリープが発見された場合には、その場で切除することも可能です。40代、50代と年齢が上がるにつれて大腸がんの発生率も増加するため, 症状がない方でも、50歳を目安に一度大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。特に、ご家族に大腸がんや大腸ポリープの既往歴がある方は、より早い時期からの検査をご検討ください。
当院、札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、最新の内視鏡システムを導入し、内視鏡専門医が丁寧に検査を行います。鎮静剤を使用した無痛内視鏡検査も可能ですので、痛みに不安がある方も安心して検査を受けていただけます。また、土曜日・日曜日も検査を実施しており、平日に時間が取りにくい方にも対応しております。検査枠に空きがあれば当日検査も可能です。



まとめ

今回のコラムでは、人工甘味料、特にアスパルテームの安全性と大腸の健康への影響について、最新の研究を交えながら解説しました。

現時点では、人工甘味料が直接的に大腸の疾患を引き起こすという明確な証拠は見つかっていませんが、肥満などの影響を考えると、間接的に大腸に悪影響を与える可能性があります。
大切なのは、特定の食品や成分に過度に依存するのではなく、バランスの取れた食生活、適度な運動、規則正しい生活を心がけることです。そして、大腸の健康を守るためには、定期的な大腸がん検診、特に大腸内視鏡検査が非常に重要です。
大腸の健康が心配な方は、ぜひ一度、当院での大腸カメラ検査をご検討ください。些細なことでも構いませんので、ご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。皆様の健康な毎日をサポートできるよう、スタッフ一同尽力してまいります。
札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、皆様のご来院を心よりお待ちしております。


内視鏡検査は札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックがおすすめです!