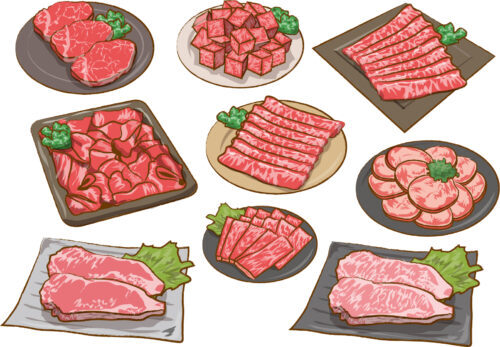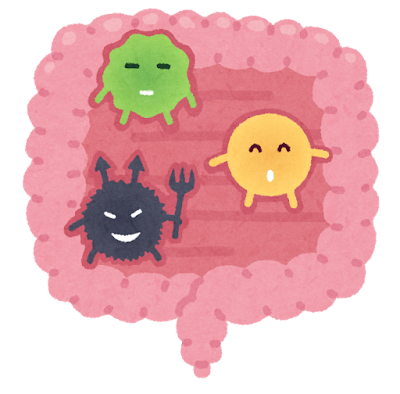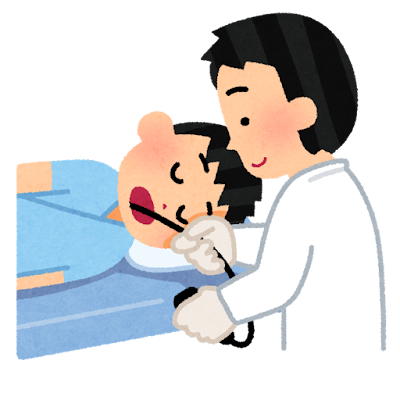2025年11月14日

こんにちは!札幌胃と大腸の内視鏡クリニック栄養士の田中です!
いつも当院のコラムを読んでいただきありがとうございます。
当クリニックには「慢性的なお腹の不調が気になる」「最近腸活を始めてみたいと思っている」「食事で病気の予防をしたい」
そんな思いを抱えた患者様が数多く訪れます。
お腹の状態は日々の生活リズムやストレス、食事内容によって大きく左右され、体調のバロメーターとも言えるほどデリケートです。
特に大腸がんは日本人にとって身近でありながら、適切な食事と定期的な検査の組み合わせで予防・早期発見が期待できる病気でもあります。
検査だけではなく毎日の「食べる」という行為こそがご自身の健康を守る重要な習慣となります。
そのため、当院では医学的観点からだけではなく「食からの健康づくり」を皆様に寄り添ってサポートしたいという思いから、栄養士監修によるレシピを発信いたします。
栄養バランスはもちろんのこと、美味しさや作りやすさ、継続しやすい工夫にもこだわっており、忙しい方でも無理なく取り入れられる内容です。
この記事では当クリニックの栄養士が監修した、胃腸にやさしく大腸がん予防にも役立つレシピを紹介します。
「健康のために何から始めて良いかわからない」という方にも気軽に一歩踏み出していただける内容となっています。
毎日の食事が変われば、お腹の調子も、未来の健康も変わっていきます。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
スープや炒め物にも使える万能米麹カレーペースト

材料
・米麹(乾燥)100g
・トマトピューレ(もしくはカットトマト缶)200g
・玉ねぎ 1/2個
・にんにく 20g
・生姜 20g
・カレー粉 20g
・塩 30g
作り方
1.全ての材料をフードプロセッサーにかけ、全体がなめらかになるまで混ぜる。フードプロセッサーがない場合は、玉ねぎ、にんにく、生姜をすりおろし、ボウルに全ての材料を入れて混ぜ合わせる。
カットトマトを使用する場合は手で潰してもOK
2.ジップロック(袋)に1の材料を入れて、ジッパーは完全に閉じずに、2~3cm分のすき間を開けて封をする
3.炊飯釜の中に布巾を敷き、その上にジップロックをのせる。
炊飯器の蓋を少し開け、保温ボタンを押し6~7時間麹を発酵させる。
麹が指で潰せる程度に柔らかくなったら完成。
※冷蔵保存で約2週間保存が可能
▲ポイント▲
1. 小麦粉・ショートニング・乳化剤不使用で、体にやさしい!
市販のカレールウには、風味やとろみを出すために小麦粉・ショートニング・乳化剤などが使われていることが多いですが、これらの添加物はアレルギーの原因になったり、消化に負担をかけることがあります。
このカレールウは、小麦粉・ショートニング・乳化剤不使用だから、
・小麦アレルギーの方
・胃腸が弱い方
・小さなお子さま
でも安心して食べられるのが嬉しいポイント。
また、シンプルな原材料は素材の味を引き立て、食後も軽やか。腸にやさしい「ナチュラルカレー」として毎日の食卓にぴったりです。
2. 米麹のオリゴ糖と食物繊維で腸内環境を整える
米麹には、腸活に欠かせないオリゴ糖と食物繊維が豊富に含まれています。
オリゴ糖は腸内の善玉菌(ビフィズス菌など)のエサになり、腸内フローラを整えます。
食物繊維は腸のぜん動運動を促し、老廃物をスムーズに排出するサポートをしてくれます。
これにより、腸内のバランスが整い
✅ 便秘解消
✅ お肌の調子アップ
✅ 免疫力向上
などのうれしい効果が期待できます。
「カレーなのに腸活になる!」というのは、まさに米麹の力。発酵食品を日常に取り入れる絶好のチャンスです
3. 辛味が強いときは「りんご」や「はちみつ」でまろやかに
辛味のあるカレーも、すりおろしたりんごやはちみつを加えることで自然な甘みとまろやかさがプラスされます。
りんごにはペクチン(水溶性食物繊維)が含まれており、腸内の善玉菌を増やす働きがあるので、ここでも腸活効果がアップ!
はちみつにもオリゴ糖が含まれており、腸内環境を整えるのにぴったりです。
さらに、りんごの酸味とはちみつのコクがカレーの旨味を引き立ててくれるので、お子様でも食べやすい優しい味わいに仕上がります。
※1歳未満のお子様にはちみつを与えないよう充分注意してください
4. とろみが足りないときは「水溶き片栗粉」で調整
市販ルウのように小麦粉を使っていない分、もし「もう少しとろみがほしいな」と感じたときは、水溶き片栗粉を少しずつ加えながら調整しましょう。
ポイントは
火を止めてから加えること
よく混ぜてから再度軽く加熱すること
片栗粉はでんぷん質なので、小麦粉よりも消化に優しく、腸にも負担をかけません。
これで、体にもやさしい万能調味料の出来上がりです。
私たちの健康を支える上で、「腸」は中心的な役割を果たしています。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、食べ物の消化・吸収だけでなく、免疫の70%以上を担い、メンタルやホルモンにも関わる重要な臓器です。そんな腸を元気に保つためには、日々の食事が大切です。
栄養素の特徴と腸への具体的な効果
今回は、腸活に役立つ6つの食材――米麹、トマト、玉ねぎ、にんにく、生姜、カレー粉に注目し、それぞれの栄養素の特徴と腸への具体的な効果を詳しくご紹介します。
1. 米麹(こめこうじ)
栄養素の特徴:
米麹は蒸したお米に麹菌(アスペルギルス・オリゼ)を繁殖させて作る発酵食品です。ビタミンB群(特にB1、B2、B6)、葉酸、ナイアシンなどのビタミン類を含み、またアミラーゼやプロテアーゼ、リパーゼといった消化酵素が豊富です。さらに、麹菌の作用で生成されたオリゴ糖やグルコースも含まれています。
腸への効果:
米麹に含まれるオリゴ糖は腸内の善玉菌(特にビフィズス菌)の栄養源となり、腸内環境の改善に貢献します。また、消化酵素は食べ物の分解を助けるため、胃腸の負担を軽減し、便通改善にも寄与します。さらに、発酵食品である米麹自体が腸内細菌に好影響を与え、腸内フローラの多様性を高めると考えられています。
2. トマト
栄養素の特徴:
トマトはリコピン、ビタミンC、カリウム、葉酸、食物繊維などが豊富な緑黄色野菜です。特に注目すべきはリコピンで、これは強力な抗酸化物質で、細胞の老化を防ぐ働きがあります。また、水溶性・不溶性両方の食物繊維を含んでいる点も重要です。
腸への効果:
食物繊維は腸のぜん動運動を促進し、便のかさを増やして排便をスムーズにします。また、リコピンの抗酸化作用が腸内の炎症を抑えることで、腸のバリア機能を保護します。さらに、トマトの水分とカリウムが体内の水分代謝を整え、むくみや便秘の改善に役立つ可能性があります。
3. 玉ねぎ
栄養素の特徴:
玉ねぎは、フルクタン(イヌリン)というプレバイオティクス成分を豊富に含み、腸内の善玉菌を育てる効果があります。また、硫化アリルやケルセチンといった抗酸化物質も豊富で、血液をサラサラにする働きも知られています。
腸への効果:
フルクタンは腸内で発酵され、短鎖脂肪酸(酪酸・酢酸など)を生み出します。これらは腸内のpHを下げて悪玉菌の増殖を抑制し、腸内フローラを善玉菌優位に保つことに寄与します。さらに、玉ねぎに含まれるオリゴ糖は整腸効果があり、便通改善や腸管免疫の活性化が期待されます。
4. にんにく
栄養素の特徴:
にんにくの代表的な栄養成分は、アリシンという硫黄化合物で、強い抗菌・抗ウイルス作用を持ちます。また、ビタミンB6やマンガン、セレンなどのミネラルも豊富に含まれています。
腸への効果:
アリシンは腸内の悪玉菌や病原菌の増殖を抑える働きがあるとされ、腸内のバランスを整えるのに役立ちます。さらに、にんにくはプレバイオティクスとしても働き、善玉菌の定着を促進する可能性があります。腸内環境の整備を通して、全身の免疫力アップにもつながります。
5. 生姜(しょうが)
栄養素の特徴:
生姜には、ジンゲロールとショウガオールという成分が含まれており、これらは体を温め、血流を促進する作用があります。さらに、抗炎症作用や抗酸化作用もあり、消化器官への効果が注目されています。
腸への効果:
生姜は胃腸の血行を促し、胃液の分泌を活発にして消化を助ける働きがあります。また、腸の運動(ぜん動)を刺激し、便秘解消に効果をもたらします。冷えによって腸の動きが低下している人にも特に効果的です。さらに、抗炎症成分が腸の炎症を抑え、腸粘膜の修復にも寄与します。
6. カレー粉(ミックススパイス)
栄養素の特徴:
カレー粉には複数のスパイス(ウコン、クミン、コリアンダー、フェヌグリーク、唐辛子など)がブレンドされています。特に注目されるのがウコンに含まれるクルクミンというポリフェノール成分で、抗酸化・抗炎症作用が非常に強力です。
腸への効果:
クルクミンは腸粘膜の炎症を抑えると同時に、腸内細菌叢のバランスを整えることが報告されています。また、クミンやフェヌグリークには消化促進作用があり、胃腸の負担を軽減します。唐辛子のカプサイシンも少量なら腸の刺激となってぜん動運動を促す働きがあり、カレー粉全体として「腸の動きを活性化するブレンド」と言えます。
まとめ
このように、米麹、トマト、玉ねぎ、にんにく、生姜、カレー粉は、それぞれが腸内環境を整える強力な栄養素を持っています。これらを組み合わせて調理すれば、腸をいたわるだけでなく、免疫力の向上や疲労回復、美肌、メンタル安定など、さまざまな健康効果が期待できます。
これらの食材を使った腸活レシピとして、「発酵トマトカレー」や「米麹入りベジスパイススープ」などもおすすめです。日々の食事に取り入れて、内側から健康を育ててみてはいかがでしょうか?
札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックは消化器内科として、治療やがんの早期発見に加え、予防の観点から食事面でも皆様の健康をサポートしています。
本記事をお読みいただき、ありがとうございます。何かご不明な点やお悩みがございましたら、札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックまでご相談ください。