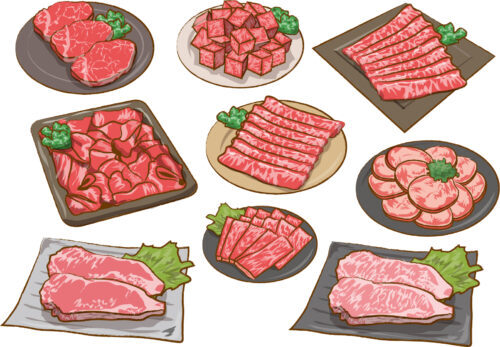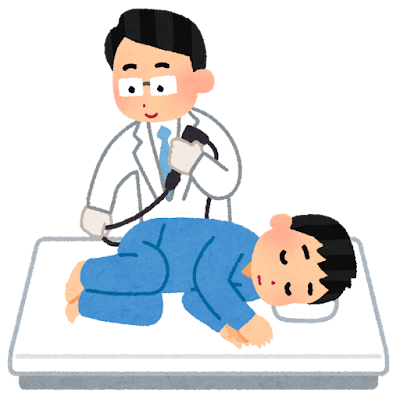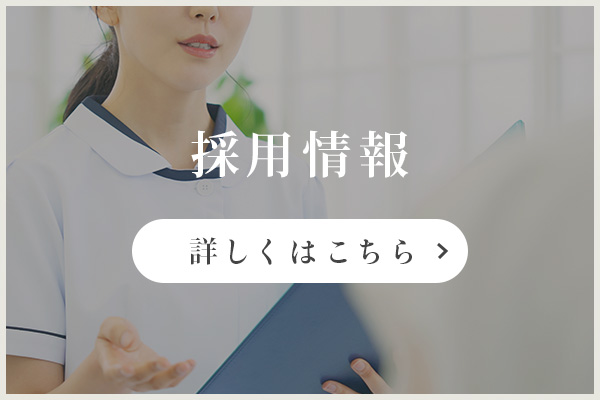2025年11月21日

こんにちは!札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック栄養士の田中です!
本日のブログは前回お話ししたFODMAP(フォドマップ)の後半の内容となります。
この記事では、海外で盛んに研究が行われ、多くのIBS(過敏性腸症候群)、IBD(炎症性腸疾患)患者さんに実際に処方されている低FODMAP(フォドマップ)食について解説していきたいと思います。
低FODMAP食は現在進行形で食事療法のプロセスや科学的エビデンスの構築が行われている食事療法です。低FODMAP食のコンセプトとプロセスを紹介させていただきます。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
IBS(過敏性腸症候群)に対する低FODMAP食の効果
IBS(過敏性腸症候群)患者に対する低フォドマップ(FODMAP)食の効果を検証したこれまでの観察研究・ランダム化試験では、低FODMAP食により、50-76%のIBS患者で消化器症状の改善が認められています。
実際にアメリカの消化器内科で低FODMAP食の臨床試験に携わったり、実際に患者に低FODMAP食を提供していた経験でも、およそ約半分の方で効果がある一方で、効果がない方も同程度いた印象です。
IBS患者に対する低FODMAP食の代表的な試験として挙げられるのが2016年に発表された米国で実施された92名のIBS下痢型患者を対象としたランダム化試験です。
この試験では、低FODMAP食群は、英国における標準的なIBSに対する食事指導(カフェイン、アルコールを避ける、少量頻回の規則正しい食事、食物繊維を控える等)のIBS症状に対する効果の比較を行いました。
その結果、低FODMAP食郡の52%の患者でIBS症状が改善し、特に腹痛、膨満感、便回数などの消化器症状に関しては、英国における標準的なIBSに対する食事指導群と比べ有意な改善が確認されました
IBD(炎症性腸疾患)に対する低FODMAP食の効果
IBD(炎症性腸疾患)患者のうち約1/3の方は、寛解期で炎症が落ち着いているにもかかわらず腹痛・下痢等の消化器症状を有していると言われています。
以前から消化器症状と食事の関係は注目されており、グルテン除去食やラクトース除去食などの食事療法が試されてきました。
その中でも最も科学的なエビデンスが構築されてきたと言われるのが低FODMAP食です。
イギリスで行われた臨床試験では、消化器症状が安定している寛解期IBD患者が、FODMAPが含まれる食事を試してみた結果、複数のFODMAPがIBD患者の消化器症状悪化に繋がったことが確認されました。
また、寛解期IBD患者の消化器症状に対する低FODMAP食の効果を検証した複数の臨床研究結果を解析したメタアナリシスも行われており、低FODMAP食が、寛解期IBD患者の下痢、腹痛、膨満感、疲れ、吐き気などの症状を改善させることが確認されています。
これらの結果から、FODMAPが寛解期IBD患者の消化器症状の原因の一つであり、FODMAPを制限することにより消化器症状が改善される可能性が示唆されました。
低FODMAP食の腸内細菌に及ぼす影響
一方で、低FODMAP食が腸内細菌の構成に及ぼす影響が懸念されています。
例えば、IBS患者と健常人を対象として、低FODMAP食とオーストラリアの一般的な食事が腸内細菌に及ぼす影響を検証した試験では、低FODMAP食により、善玉菌のような身体に良い腸内細菌が減少することが確認されました。
しかし、低FODMAP食による腸内細菌環境の変化は、低FODMAP食をやめることで元に戻ることも確認されています。
また長期的な低FODMAP食に関する効果・安全性についても研究結果が報告され始めており、18名のIBS患者さんを対象とした試験では、低FODMAP食を行った患者さんの多くが12ヶ月後も消化器症状改善が続き、善玉菌と言われるbifidocteriaは開始時と同程度であったことが確認されました。
以上、低FODMAP食のコンセプトと、IBDに関するエビデンスについて紹介させていただきました。
低FODMAP食の3つのプロセス
前回のブログでもお伝えしたように、低FODMAP食は、FODMAPが含まれる食品を制限する(=食べない)という食事療法ではありません。あくまで消化器症状をコントロールするための食事療法と言われています。
よって、FODMAPが含まれる食品 = 悪(一生食べてはいけない)とは限りません。低FODMAP食を通して、自分の消化器症状の原因となるFODMAPの種類を特定します。
その後、その自身の消化器症状を引き起こすFODMAPを避けつつ、徐々に栄養的にバランスが良い食事を摂ることによって、生活の質を上げていくことがゴールになります。
低FODMAP食は、以下の3つのプロセスに分類されます。制限期間、再導入期間、個別化された食事の継続です。
準備:生活習慣のベースをつくる
低FODMAP食を始める前に、まずは生活習慣を整えましょう
規則正しい生活を送る
生活習慣を整えるには、規則正しい生活を送るのがよいとされています。できるだけ毎日同じリズムで生活しましょう。
食事はなるべく時間を決めて食べる
食事の時間を固定すると比較的簡単に規則的な生活リズムが作れます。時間が決められないときは、可能な範囲でよいので朝ごはんは〇時から〇時くらい、昼ごはんは、夜ごはんは……とおおよその時間を決めておきましょう。
1日3食食べる
時間を決めて3食食べると、生活リズムが整います。また、1日に必要な栄養素が摂取しやすくなります。1日分のビタミンや食物繊維などをとるのに必要な野菜(350g以上)を1食で摂取するのは困難です。主食や主菜も1日分を3食に分けるほうが食べやすくなります。
主食、主菜、副菜をそろえる
献立を立てるときは、一汁三菜、一汁二菜、一汁一菜という日本の食事の形式に当てはめて考えるのがおすすめです。量のバランスは、全体の半分が主食、もう半分がおかずとなるのが理想的。おかずは、3分の1が主菜、3分の2が副菜になるようにすると整います。
生活習慣が整ったら次は低FODMAP食の開始です。
Step1:制限期間
高FODMAP食品を控える[目安期間:約3週間]
以下の表を参考に、高FODMAP食品を極力摂取しないよう制限します。

「食事日記」に食事内容と、お腹の症状がどう変化したかを記録しておきましょう。この期間を通して、FODMAPが自身の消化器症状に影響しているのかを確認します。
高FODMAP食品を控えても症状がよくならない場合は、「食事日記」を見返してきちんと除けていたかを確認します。高FODMAP食品を制限しているにもかかわらず、症状が改善しない場合は、FODMAPが原因ではない可能性があります。
また、FODMAPが原因で消化器症状が起きている場合は、この制限期間内で消化器症状の改善が見られます。
1週間程度で症状の改善を実感できる患者さんもいれば、2~3週間後に症状の改善を実感し始める患者さんもおり、症状の変化の出るタイミングは人によって異なってきます。
Step2:再導入期間
FODMAPを試す[目安期間:約6週間]
この再導入期間では、消化器症状の原因となる特定のFODMAPを見つけることが目的となります。最初の制限期間と同様にFODMAP制限を継続しつつ、それぞれのFODMAPを個別に少しずつ量を増やしながら食べて消化器症状が出るか出ないかを確認していきます。食べても消化器症状が出なければ、その食品はその量まで食べられる食品と判断します。
食品の試し方として、一つの食材を選び、それを少量から徐々に増やしていくかたちをとります。
具体的には、以下のようなFODMAPグループに含まれる食材を順番に試していきます。

(米国登録栄養士がゼロから教える栄養学「低FODMAP食」より抜粋)
例えば、ポリオールが含まれるグループでは、1日目に桃を半量、2日目に桃を3/4個、3日目に桃を1個というかたちです。
その途中で消化器症状が発生した場合は、消化器症状が発生するまでの量は、体が許容できることがわかります。また消化器症状が発生しなかった場合、試した量までは体が許容できることがわかります。
もし消化器症状が現れた場合は、その食事を再導入することをストップし、消化器症状がなくなるまで(通常3-5日程度)低FODMAP食のみを継続し、その後次の食材を試します。
また同じFODMAPグループであっても食材によって消化器症状の有無が変わることもあります。
ただリストにある全ての食材を試すのとかなりの時間がかかってしまうので、自分が普段食べていたもしくは食べたい食材から試されることをお勧めします。
最後に、再導入期間を続けていると、どの食材を試したかがわからなくなることがありますので、必ずどの食材を試し、その結果がどうだったのかについては記録を残しましょう。
個々のFODMAPは、化学構造や消化プロセスが異なるため、どのFODMAPが一番消化器症状に影響を与えるかは患者さん1人1人で異なります。
Step3:個別化された食事の継続
原因のFODMAPだけ省く
この期間は、再導入期間で得られた結果を踏まえ、症状が悪化したFODMAPグループが含まれる食材のみを制限し、消化器症状を抑えつつ、栄養バランスの良い食事を摂ることによって、生活の質をあげることが目標となります。栄養バランスの良い食事を取るコツとしては、再導入期間で見つけた消化器症状のトリガーとなるFODMAPグループに分類される食材を避けつつ、低FODMAP食、消化器症状のトリガーではないFODMAPグループから、様々な種類の食品を食べることとなります。
多くの食品を除去すると、選択肢の少ない食卓となり、栄養面でも偏りが生じます。除去する食品を減らすのに加え、お腹と全身の健康のために栄養バランスも意識しましょう。
以上、低FODMAP食の具体的なプロセスとその留意点について紹介させていただきました。
まとめ
最後に、低フォドマップ(FODMAP)食を行う上での留意点をまとめさせていただきます。
適正な体重を維持する
低FODMAP食は、制限食のため、短期的に炎症などが悪化するケースはあまりないと思いますが、極度の栄養不足や体重減少、ビタミン・ミネラル不足による疲れなどには注意が必要です。普段体重を意識されてない方は、こまめに体重を測ることをおすすめします。
FODMAP制限期間を長期間続けない
全てのFODMAPを制限しながら、バランスの良い食事をとるのはとても難しいです。低FODMAP食では、FODMAP制限期間で止まらずに、再導入期間、維持期間まで進みましょう。
IBD患者では自主的な食事制限により栄養素が不足することが多いので、消化器症状の引き起こすFODMAPのみを取り除くこと、そして栄養バランスの良い食事を継続することが重要になります。
また、腸内細菌の多様性を保つうえでも、様々な食物を摂取することが望ましいです。
低FODMAP食では上記に注意しながら、必要に応じて主治医の先生などに指示を仰ぎながらプロセスを進めていただければと思います。
以上、FODMAP(フォドマップ)について前半後半に分けてお話しさせていただきました。
お腹の不調は…
当院では、そんな皆さまのお腹の悩みにしっかり寄り添い、丁寧にサポートいたします。
「これくらい大丈夫かな…?」と思う前に、ぜひ一度ご相談ください。
また、健康維持のためには 定期的な大腸カメラ検査 と バランスの良い食事 がとても大切です。
未来の自分のために、今できる一歩を踏み出してみませんか?
本記事をお読みいただきありがとうございます。何かご不明な点や、お悩みがございましたら、札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。