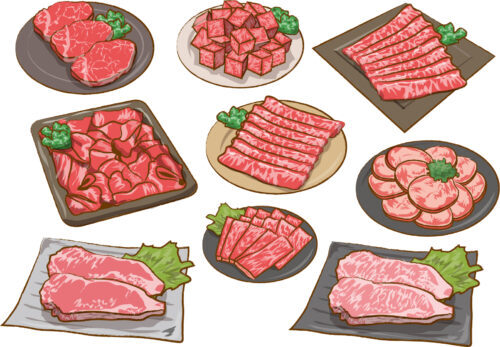2025年11月27日

こんにちは!札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック栄養士の田中です!
「手足が冷えてつらい」「お腹だけ冷たい」
そんな冷えの悩みは、季節に関係なく多くの方が抱えています。特に女性では、約7割が“冷え性”と自覚しているとも言われ、日常的な体質として受け止められていることが多いようです。
しかし、この“冷え”は単なる不快症状で終わりません。
実は 大腸の働き と深く関わっており、便秘・下痢・腹痛といった腸の不調だけでなく、腸内環境全体を乱す原因にもなるのです。
さらに見逃してはいけないのが、
「冷えのせいだと思っていたら、実は大腸の病気が隠れていた」
というケースが一定数存在すること。
今回のブログでは、冷えが腸に与える影響を医学的な視点からわかりやすく解説し、どんな症状があるときに検査を考えるべきか、そして“冷えの体質”とどう付き合えばよいのかを深掘りします。
「冷え性だからしょうがない」と放置しているあなたへ。
腸からのサインを見逃していませんか?
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
冷えるとどうして大腸に影響が出るのか?
体が冷えると、大腸の働きが弱まりやすいのには明確な理由があります。ここではそのメカニズムを整理してみましょう。
① 血流が低下し、大腸の動きが鈍くなる
寒さを感じると、体は内臓を守るために血管をぎゅっと収縮させます。
血流が落ちる→腸に届く血液も少なくなる→腸の動きが低下。
その結果
・便が滞留して便秘に
・ガスが溜まりやすくなる
・腹部に張りが出る
などの症状につながります。
特に冬場や冷房のきいた環境では症状が強く出やすく、
「冬だけ便秘になる」
という方はこのパターンに当てはまることが多いです。
② 自律神経が乱れ、腸のリズムが乱れる
腸の動きをコントロールしているのは自律神経です。
ところが冷えにより血流が悪くなると、自律神経が乱れやすくなり、腸のリズムが不安定になります。
特に過敏性腸症候群(IBS)の人はもともと自律神経が敏感なため、冷えによって症状が悪化しがちです。
③ 腸内環境が悪化し、善玉菌が働きにくくなる
腸内細菌は“温度”に非常に敏感です。
適温は36〜38度前後とされ、この範囲で最も活発に働きます。
しかし、体や腹部が冷えると腸の温度も下がり、善玉菌の活動が低下。逆に悪玉菌は冷えやストレスの影響を受けにくいため、腸内バランスが崩れやすくなります。
冷え性の方が感じやすい“大腸のサイン”
あなたに当てはまるものはありませんか?
・朝スッキリ出ない
・トイレに行っても残便感がある
・便秘と下痢を繰り返す
・お腹の張りが常にある
・お腹を触ると冷たい
・最近便が細くなってきた
・冷えると急にお腹が痛くなる
これらは冷えによる腸の不調で説明できることもありますが、
すべてが冷えのせいとは限りません。
特に「便が細くなる」「トイレに行った後もスッキリしない」「以前と便通のリズムが変わった」などは、大腸の変化が隠れている可能性もあります。
“冷えで不調”と思われがちな症状の中に、病気が隠れていることも
冷えと腸の関係は深いものの、冷え性の方には“誤解”も多いのが現実です。
「冷えたからお腹を壊したんだろう」と考えて放置してしまうこと。
しかし、その症状が以下のようなものであれば、
冷えだけでは説明できない場合もあります。
・便が極端に細くなってきた
・便秘が急に強くなった
・便が黒い・血が混じる
・腹痛が慢性的に続く
・以前よりガスが増えた
・食べていないのにお腹が張る
これは大腸ポリープ、大腸炎、虚血性腸炎、さらには大腸がんの初期症状として現れることがあり、“冷え”と誤認されやすい傾向があります。
冷える季節にこれらの症状が出るとつい“冷えのせい”と考えてしまいますが、
実は腸からのSOSであることも決して珍しくありません。
症状が2週間以上続くなら、検査を検討するタイミング
どんな腸の症状でも、
「2週間を超えて続く」
これは大腸からのサインとして受け取ったほうがよい目安です。
冷えで一時的に腸の調子が乱れることはありますが、通常であれば数日〜1週間ほどで戻ってきます。
以下に当てはまる場合は、冷えではなく“腸自体の変化”の可能性があります。
特に40代以降は大腸ポリープが増える年代。
「冷えが原因だと思っていたけど、検査したらポリープが見つかった」というケースは本当に多いです。
冷え性の方こそ、一度“大腸カメラ”で腸の状態を確認すると安心
冷えによる腸の不調は、多くの場合セルフケアで軽くなりますが、“便通の変化” や “お腹の張り”“便が細くなる” といったサインが続く場合は、冷えだけでは説明できないケースがあります。
大腸ポリープや初期の大腸がんはほとんど症状がないため、
「冷えると調子が悪いだけ」
と感じている方ほど発見が遅れやすい傾向があります。
だからこそ、次のような変化がある方は、一度大腸の状態を確認しておくと安心です。大腸カメラ検査は、腸の中を直接見られる唯一の方法です。
・小さなポリープも発見できる
・その場で切除が可能
・鎮静剤を使用するので眠ったまま検査ができる
「冷え性で腸が弱い体質だから…」とずっと悩んでいた方が、
検査を受けたことで原因が明確になり、
「もっと早く検査すればよかった」と言うことも珍しくありません。
“冷えなのか、腸の異常なのか”を見分けるためには、大腸カメラが最も確実な方法です。
今日からできる腸を温める生活習慣
大腸カメラ検査と一緒に腸のケアも始めましょう
① 下腹部を温める習慣をつける
腹巻き・カイロは腸の血流を上げてくれます。
② 温かい食事を中心に
根菜類、味噌汁、乾燥生姜などは腸を温める効果が高いです。
③ 冷たい飲み物を減らす
氷入りの飲料やキンキンの水は腸を冷やします。なるべく常温で。
④ 適度な運動で血流改善
ウォーキングやストレッチだけでも腸が動きやすくなります。
これらは腸の環境を整える助けになりますが、
症状そのものの原因を取り除くものではありません。
不調が続く場合は“冷え”に責任を押し付けすぎないことが大事です。
冷えによる腸の不調は、多くの場合セルフケアで軽くなりますが、“便通の変化” や “お腹の張り”“便が細くなる” といったサインが続く場合は、冷えだけでは説明できないケースがあります。
大腸ポリープや初期の大腸がんはほとんど症状がないため、
「冷えると調子が悪いだけ」
と感じている方ほど発見が遅れやすい傾向があります。
だからこそ、一度大腸の状態を確認しておくと安心です。
検査を迷われている方へ
もし今、あなたが
冬になると腸の不調がひどくなる
冷えると必ずお腹を壊す
最近、便の状態が以前と違う
腹部の張りや痛みが長く続いている
という状態なら、
その不調が“本当に冷えのせいなのかどうか”を、一度プロの目でチェックしてみませんか?
腸の検査は、つらくなる前の「今」の段階で受けておくことが、将来の安心へつながります。
不調の原因が冷えなら、生活改善でしっかりと整えていけば良いですし、
もしポリープなどが見つかった場合でも、早期であればその場で治療できるため、その後の生活がぐっと安心になります。
冷え性の方ほど“腸の変化”を見逃さないで
冷えと腸の関係は深いですが、
すべてを冷えのせいにしてしまうと、腸からのSOSに気づくのが遅れてしまうことがあります。
だからこそ、腸に少しでも“いつもと違う”と感じる変化があれば、
どうか遠慮なくご相談ください。
あなたの腸の状態をしっかり確認できるのが、大腸カメラ検査です。
冷えで揺らぎやすい季節こそ、ご自身の腸を守るための一歩を踏み出してみませんか?
まとめ:冷えと腸の不調は深くつながっている
しかし、全てを冷えのせいにしないで
冷えによって腸の調子が乱れることは確かにあります。
しかし、冷え性の方ほど「体質だから」と放置してしまいがちです。
でも実際には、冷えに似た症状の中に 大腸ポリープや大腸がんの初期サインが隠れている ことも少なくありません。
最近、便通やお腹の状態に変化がある方は、
ぜひ一度、ご自身の腸の状態をチェックしてみてください。
当クリニックでは、患者様の負担を減らすため、鎮静剤を使用した苦痛の少ない内視鏡検査や、土日も検査が可能な体制を整えています。ご自身の健康を守るために、ぜひ一歩踏み出してください。
本記事をお読みいただきありがとうございます。何かご不明な点や、お悩みがございましたら、札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。