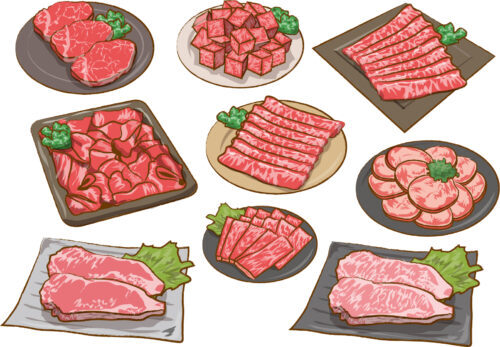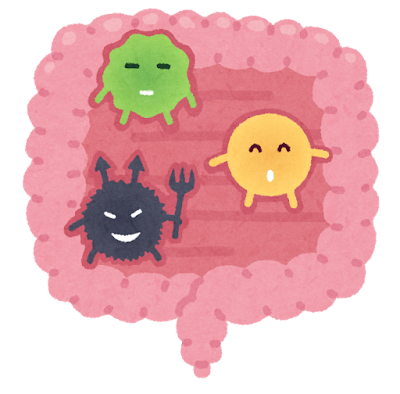2025年8月25日

こんにちは!札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック事務長の高橋です!
お寿司やお刺身など、新鮮な海の幸は私たちの食生活に欠かせないものですよね。
しかし、その美味しさの裏には、潜んでいるかもしれない小さな危険、アニサキスの存在があります。
特に、お寿司が好きでよく食べる方にとって、「もしかしたらアニサキスに感染してしまうかも…」と不安を感じることもあるのではないでしょうか。
この記事では、近年増加しているアニサキス食中毒について、その原因や症状、予防法、そして万が一感染してしまった場合の対処法まで、専門的な知見と分かりやすい解説でお伝えします。
この記事を読めば、アニサキスに関する疑問や不安が解消され、これからも安全に美味しいお寿司を楽しむための知識が身につきます。
「お寿司を食べてから胃がキリキリ痛む…」「アニサキス食中毒ってどんな症状が出るの?」といった疑問を持つ方、そして「アニサキスについて正しい知識を身につけたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次
アニサキスはなぜお寿司に潜んでいるのか?
アニサキスとは、クジラやイルカといった海洋哺乳類を最終的な宿主とする寄生虫です。
その幼虫は、サバ、サケ、アジ、イワシ、カツオ、イカなど、私たちが普段口にする多くの海産魚介類に寄生しています。
特に、これらの魚介類を生で食べる習慣のある日本では、アニサキスによる食中毒が諸外国に比べて圧倒的に多く発生しています。
アニサキスは、魚が生きている間は主に内臓にいますが、魚が死んで鮮度が落ちてくると、内臓から筋肉(身)へと移動する性質があります。
そのため、内臓を素早く取り除かずに放置しておくと、感染の危険性が高まるのです。
アニサキス食中毒の主な原因となる寿司ネタ
アニサキスによる食中毒の原因となる代表的な魚介類には、サバ、サンマ、アジ、イワシ、サケ、カツオ、イカなどが挙げられます。
これらの魚は、寿司ネタや刺身として生で食べることが多いため、特に注意が必要です。
新鮮な魚を選び、適切に処理されたものを食べることが、アニサキス食中毒を予防する上で非常に重要です。
鮮度の良い魚でもアニサキスは存在するのか?
「鮮度が良ければアニサキスはいないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、アニサキスは鮮度に関わらず魚介類に寄生している可能性があります。
鮮度の良い魚の場合でも、内臓の近くや筋肉中にアニサキスが潜んでいることがあり、目視での確認や適切な下処理が欠かせません。
プロの寿司職人や鮮魚店の職人は、魚をさばく際にアニサキスがいないか細かくチェックしています。
アニサキス感染を疑う症状と具体的な対応策 アニサキスが寄生している魚介類を摂取すると、2~10時間後に激しい腹痛や吐き気、嘔吐といった症状が現れることが一般的です。
これは、アニサキスが胃や腸の壁に潜り込もうとすることによって引き起こされます。
症状の現れ方には個人差があり、みぞおちの激痛や蕁麻疹を伴うこともあります。
アニサキス食中毒の典型的な症状
アニサキス食中毒の症状は、食後数時間で突然始まるみぞおちの激痛が最も特徴的です。
痛みは断続的であったり、持続的に続いたりすることがあります。
また、何度も繰り返す嘔吐や吐き気も伴います。これらの症状は、胃や腸にアニサキスが食いついていることによるものです。中にはアレルギー反応として、蕁麻疹やアナフィラキシーショックを起こすこともあります。
アニサキス感染を疑った場合の対処法 もし、お寿司や刺身を食べた後に、上記のような激しい腹痛や嘔吐といった症状が出た場合は、アニサキス食中毒の可能性を疑い、速やかに医療機関を受診しましょう。
放置すると重症化する恐れもあるため、自己判断で様子を見ず、早めの受診が重要です。
特に消化器内科や内視鏡専門のクリニックを受診することで、スムーズな診断と治療が期待できます。
アニサキス食中毒を予防する確実な方法 アニサキス食中毒は、適切な予防策を講じることで避けることができます。お寿司や刺身を安全に楽しむために、以下の予防法を覚えておきましょう。
アニサキスに効果がある予防法 アニサキスは熱と冷凍に弱いという性質があります。最も確実な予防法は、「加熱」と「冷凍」です。
加熱する: 食材の中心部が60℃で1分以上、または70℃以上で瞬間的に加熱されるとアニサキスは死滅します。
冷凍する: -20℃以下で24時間以上冷凍することでアニサキスは死滅します。市販の冷凍保存されたシメサバなどが安全なのはこのためです。
目視で確認: 魚の身を切り分ける際に、白い糸のようなアニサキスがいないか注意深く観察し、発見したら取り除くことも有効です。ただし、これだけでは100%の予防は難しいです。
アニサキスに効果がないとされている予防法 アニサキスは、一般的な調理法では死滅しないため注意が必要です。
お酢や塩、ワサビ: シメサバのように塩や酢で調理したり、わさびや醤油につけて食べたりするだけでは、アニサキスの幼虫は死滅しません。
魚を細かく刻む: 魚を細かく刻んでも、アニサキスが完全に死ぬわけではありません。
プロの寿司職人や鮮魚店が実践している対策とは? 「お寿司屋さんでアニサキスに当たったという話はあまり聞かない」と感じる方もいるかもしれません。
それには理由があります。プロの寿司職人や鮮魚店は、アニサキス食中毒を未然に防ぐために、様々な対策を講じています。
寿司ネタの選定と下処理のプロフェッショナルな技 プロは、魚の仕入れ段階から鮮度を厳しくチェックします。
また、魚をさばく際には、内臓をすぐに取り除き、身にアニサキスが移動するのを防ぎます。
さらに、ネタを切り分ける際に、光にかざすなどして、肉眼でアニサキスの有無を細かく確認するのもプロの技術です。
一部の魚種では、一度冷凍処理されたものを使用することもあります。
養殖魚と天然魚におけるアニサキスのリスク 一般的に、養殖魚はアニサキスのリスクが低いとされています。これは、養殖の過程でアニサキスの宿主となるオキアミなどを排除した餌を与えているためです。
しかし、中には畜養された天然のサバのように、アニサキスがいる可能性のある魚も存在します。そのため、天然魚・養殖魚に関わらず、適切な処理が重要になります。
事務長エピソード:まさか自分がアニサキスに?
実は、私自身もつい先日、アニサキスに苦しんだ経験があるんです。
週末に地元の新鮮なイワシのお刺身を食べた夜から、急にみぞおちがズキズキと痛み始めました。「食べ過ぎかな?」と軽く考えていたのですが、夜になっても痛みは治まらず、次第にキリキリと胃が締め付けられるような激痛に変わり、一晩中眠れませんでした。
翌朝、これはただ事ではないと思い、専門のクリニックを受診しました。
問診で「最近、生魚を食べましたか?」と聞かれ、前日のイワシの刺身のことを伝えると、すぐに内視鏡検査をすることに。そして、胃カメラのモニターに映し出されたのは、胃の壁にしっかりと食いついた白い糸のようなアニサキスでした。
先生が特殊な鉗子(かんし)でアニサキスを引っ張って取り除く瞬間は、痛みが走りましたが、アニサキスが除去された後は、あれほど辛かった胃の痛みが嘘のようにスッと消えていきました。
あの激痛はもう二度と経験したくありませんが、この経験を通して、アニサキス食中毒の恐ろしさと、内視鏡による早期治療の重要性を身をもって知ることができました。
まとめ
アニサキス食中毒は、私たちが普段から楽しんでいるお寿司や刺身に潜む身近なリスクです。
しかし、アニサキスの生態や予防法、そして感染してしまった場合の対処法を正しく理解していれば、過度に恐れる必要はありません。
安全に美味しいお寿司を楽しむためには、信頼できるお店で食べる、新鮮な魚を選び適切に処理をする、そして万が一症状が出た場合は、早めに医療機関を受診することが何よりも重要です。
特に、消化器内科や内視鏡専門のクリニックでは、迅速にアニサキスを除去する治療を受けることができます。
本記事をお読みいただきありがとうございます。何かご不明な点や、お悩みがございましたら、札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。